
 |
第15回 LEDで電子オルゴールを鳴らす |
LEDの原理を理解させる
超高輝度LED、電子オルゴール、リード線、乾電池(単三2本)、OHP
 |
 |
大型の |
小型の超高輝度LEDを |
LEDは普通のダイオードと構造は同じです。どちらもp型半導体とn型半導体からなっていて、順方向に電流を流すと、その接合部で自由電子とホールが再結合します。このときのエネルギーが、光の形で出てくるようになっているのがLEDです。
一方、太陽電池は、n型半導体の基盤の上に薄いp型半導体の層をのせた構造をしています。p型の層は光が透過しやすいように十分薄く作られています。これに光を当てると、p型とn型の半導体部分で、光のエネルギーのためにホールと自由電子が分離し、ホールはp型、自由電子はn型を通って、外へ流れていこうとします。
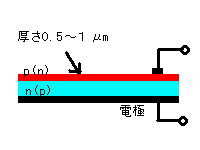 |
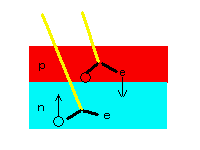 |
太陽電池の構造 |
太陽電池の原理 |
原理はその通りなのですが、実際にLEDに太陽電池の代わりをさせるためには、普通のダイオードではパワー不足のようで、超高輝度LEDぐらいでないとだめなようです。
まず、超高輝度LEDを直射日光に当て、端子間の電圧をデジタルテスターで計ってみました。
| 直径10mm程度の赤色LED | 1.58V |
| 直径10mm程度の緑色LED | 1.41V |
結構な起電力が生じることがわかります。赤と緑では、同じ大きさ同じ価格のものでは、赤の方が輝度が高いようですが、このように逆に使っても輝度の高いLEDのほうが光から電気への変換が効率的なようです。
次に、LEDの端子を電子オルゴールにつないで、直射日光を当ててみました。
| 直径10mm程度の赤色LED | なんとか曲がわかる。このときの端子電圧1.42V |
| 直径10mm程度の緑色LED | かろうじて音が聞こえる。このときの端子電圧0.74V |
やっぱり赤の方が効率がよいようです。秋の日射しで試みましたので、夏ならもっとよく鳴るかもしれません。レンズで集光するとばっちりです。OHPのレンズ付近にLEDをかざしてもよく鳴ります。
また、電子オルゴールの代わりに電卓に接続してみました。さすがに電卓は電子オルゴールより消費電力が少なく、赤色LEDでも緑色LEDでも、電卓を作動させることができました。計算もできます。
このように、超高輝度LEDを使えば、太陽電池の代わりがつとまることがわかりました。
さらに効率を上げるために、赤色LEDを7つ並列にしたものを作ってみました。一つ一つは直径5mm程度の超高輝度LEDです。単独で使うよりも7倍の電流を生むことができます。これを使えば太陽が出ていない日でも、OHP用のランプに直接近づけると電子オルゴールが鳴ります。
なお、太陽電池は普通の乾電池とは違って電流源として働くので、太陽電池を2つ並列にして使用すれば2倍の電流が得られます。
光を電気に変えたり、電気を光に変える装置の例は枚挙にいとまがありませんが、超高輝度LEDはその両方を1つの素子でできてしまうわけで、教材としてはなかなかおもしろいと思います。ちょうど、スピーカーとマイクが同じ構造で、電気を音に変えたり、その逆をしたりするのとよく似ています。
半導体の教材のみならず、エネルギーの教材として、いろいろ使い道がありそうに思います。
この話をパソコン通信のネットワークであるNIFTY SERVEの教育実践フォーラム【理科の部屋】でしたところ、福島県立二本松工業高等学校の山本央明先生から「逆に太陽電池に電流を流すと、太陽電池が光る」という報告をいただきました。太陽電池に10Vの電圧をかけたところ、1Aの電流が流れ、太陽電池の表面が点々と光ったということです。ただ、光らない太陽電池もあって、その原因については、現在研究中とのことです。
送信側、受信側双方に超高輝度LEDを使った光通信の実験です。杉並区立科学教育センターの河野晃さんが取り組んでおられます。
超高輝度LEDで電子オルゴールを鳴らす話は、学研トイホビーの赤尾さんから伺いました。また、太陽電池を光らせる実験は山本先生に、LED通信の話は杉並区立科学教育センターの河野晃さんに伺いました。赤尾さん、山本先生、河野さん、ありがとうございました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 元へ戻る | 力学関連 | 熱力学関連 | 波動関連 | 電磁気関連 | 原子関連 | 科学の祭典 | リンク集 |