 |
第1回 コイルとコンデンサーのリアクタンス |
【掲載】1996.03
【単元】交流
【種別】演示実験
【対象】高校3年
【実施】1995.11
- 目 的
コイルやコンデンサーの交流に対する振る舞いが、交流の周波数によって大きく変わることは、理屈では説明できますが、なかなか実感しにくいものです。また、直列共振の話もわかりづらいもの。やはり実験して実際に目でみないと!
- 準 備
低周波発信器、アンプ、豆電球(3.8V球)、ソケット、コイル、鉄芯、コンデンサー(数μF)2個、オシロスコープ
- 方 法
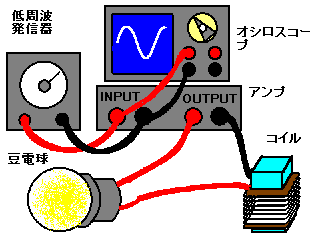 (1) コイルのリアクタンス
(1) コイルのリアクタンス
- 低周波発信器の出力をオシロで監視し、それをアンプで増幅して、豆電球(3.8V球)とコイルを直列にした回路に接続します。
- 低周波発信器の周波数を変えながら豆電球の明るさを見ます。低周波で明るく、高周波で暗くなることがわかります。周波数の高低はオシロスコープで監視します。
- 周波数を一定にしておいて鉄芯を抜き差しすると、インダクタンスが変わって豆電球の明るさが変化します。鉄芯を抜くと明るくなります。
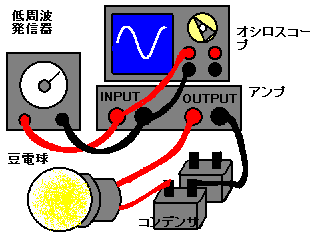 (2) コンデンサーのリアクタンス
(2) コンデンサーのリアクタンス
- 低周波発信器の出力をオシロで監視し、それをアンプで増幅して、豆電球(3.8V球)とコンデンサを直列にした回路に接続します。
- 図のように配線します。
- 低周波発信器の周波数を変えながら豆電球の明るさを見ます。低周波で暗く、高周波で明るくなることがわかります。
(注意!)あまり高周波にすると発信器のパワーがダウンして豆電球が暗くなることがあります。そうならない程度にあらかじめ各種の定数を調整しておくこと。
- 周波数を一定にしておいて、別のコンデンサーを並列にはさみます。容量が変わって豆電球の明るさが変化します。容量が増えると明るくなります。
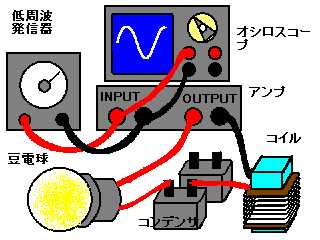 (3) 直列共振
(3) 直列共振
- 低周波発信器の出力をオシロで監視し、それをアンプで増幅して、豆電球(3.8V球)とコイルとコンデンサを直列にした回路に接続します。
- 低周波発信器の周波数を変えながら豆電球の明るさを見ます。低周波で暗く、周波数を高くすると一瞬明るい状態があって、さらに高周波にするとまた暗くなることがわかります。途中の明るい状態が直列共振の起こっている状態です。
- 周波数を一定にしておいて、別のコンデンサーを並列にはさみます。容量が変わって共振周波数が変化します。容量が増えると共振周波数は小さくなります。
この実験について
周波数を監視するためにオシロスコープを用いるのがポイント。リアクタンスの周波数依存性が一目瞭然です。
謝 辞
本実験は、大阪府理化教育研究会・標準テスト作成委員会での雑談から生まれました。委員の皆さん、ありがとうございました。
檀上 慎二


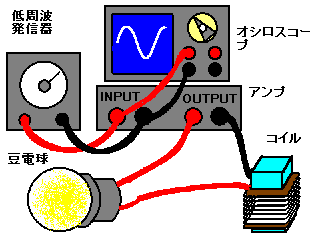 (1) コイルのリアクタンス
(1) コイルのリアクタンス
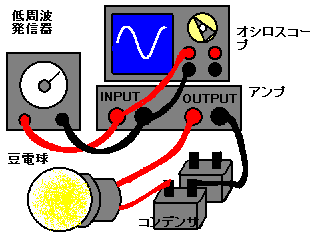 (2) コンデンサーのリアクタンス
(2) コンデンサーのリアクタンス
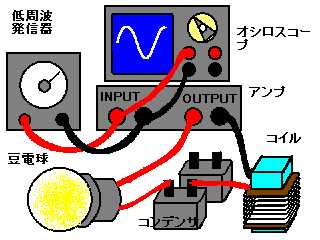 (3) 直列共振
(3) 直列共振







