
 |
第5回 熱気球 |
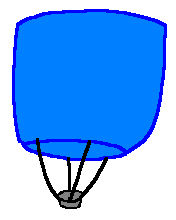
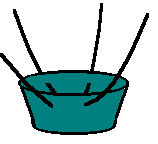
熱気球を作って上げる。
濡れ雑巾(必須!!)、ゴミ袋(0.015mm厚)、細い鉄の針金2本(60cm長)、弁当用アルミホイルの舟、セロテープ、エタノール、小ビーカー、脱脂綿、着火マン


しばらくすると袋が膨らんできます。浮力がついてきたら手を離すとフワッと浮き上がります(^_^)。しばらく天井に貼り付いたのち、やがて火が消えると落ちてきます。
エタノールが多すぎると火が床にボタボタと落ちてきます。また、舟のバランスが悪いと、火のついた脱脂綿が落ちてきます。こんなときにはあわてず騒がず、濡れ雑巾を上からかぶせるとよろしい。濡れ雑巾の準備は絶対に怠らないこと。
私はこの気球を1班1つ(人数が少なければ1人1つ)ずつ作らせますが、点火作業と消火作業は必ず私が行います。このさい生徒の持ち物、衣服に火が近づかないように注意。
また、一つの気球を消火してから別の気球を点火するようにし、あちこちで火が燃えて収拾が付かなくなるような状況は避けるようにしています。
ゴミ袋は0.015mm厚のシャカシャカいう安物がよいようです。0.03mm厚は重くてうまく浮きません。
火力が弱くてうまく上がらないときは、脱脂綿を広げるとうまくいきます。燃料にプロパノール、ブタノールなどを試してみたこともありましたが、大して変わらないようです。それよりは、脱脂綿を広げて火床面積を大きくすることが一番効果的でした。
他にもゴミ袋の口を針金で丸く広げるだとか、袋に凧糸を取り付けて遠くに飛んでいかないようにするだとか、いろいろな工夫が報告されていますが、私は面倒臭がりですのでやっていません。もっともシンプルな形で生徒に作らせています。
この実験は有名なものなので、いろいろなバージョンのものをあちこちでよく目にします。私の場合、大阪・明浄高校に勤務しておられました釜堀先生に教えていただいたものを元に、いろいろと試行錯誤しながら上のような形に落ち着きました。
書物では
「いきいき実験わくわく物理」愛知岐阜物理サークル(新生出版)
にも扱われています。
同書は他にも役にたつ実験が満載されており、物理の教師のバイブルともいえる存在です。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 元へ戻る | 力学関連 | 熱力学関連 | 波動関連 | 電磁気関連 | 原子関連 | 科学の祭典 | リンク集 |