
 |
第14回 手作り電球 |
シャーペンの芯や竹串を使って、電球を作る。
フラスコ、ゴム栓、2mm真鍮棒2本、ワニ口クリップ2個、リード線、スライダック、シャーペンの芯(B)、窒素ボンベ
 |
 |
 |
| ワニ口クリップを はんだ付け |
フラスコの中に 挿入 |
明るく輝く シャーペン電球 |
シャーペンの芯は明るく輝きます。
この光は、炭素が燃えている光ではありません。ものはすべて、温度をもっているとその温度に応じた光を出しています(熱輻射)。物体の分子の熱運動のエネルギーが光のエネルギーとして放射されるのです。
常温ではその光は赤外線なので目に見えません。しかし、高温にすると可視光線を出すようになります。
電球のフィラメントも同じで、ジュール熱のためにフィラメントが高温になり、熱輻射によって可視光線が出るようになります。
空気中だと、燃焼が起こるために、フィラメントが長持ちしません。そのために、装置をフラスコ内に入れて、窒素を充填しています。ただし、長く点灯するとフラスコ内のガスが熱膨張し、ゴム栓が飛び出ることがあるので注意が必要です。また、あまり長時間点灯を続けると、ワニ口のはんだが融けることもあります。
なお、シャーペン芯が折れるのを防ぐため、ワニ口クリップ同士を絶縁体で固定したほうがよいようです。
竹串からフィラメントを作る。
フラスコ、ゴム栓、2mm真鍮棒2本、ワニ口クリップ2個、リード線、スライダック、竹串、タンマン管、ブタンガスバーナー、アルミホイル、るつぼばさみ、灰皿、窒素ボンベ
 |
 |
 |
 |
| これが材料 の竹串 |
タンマン管で 蒸し焼き |
電極に アルミホイル |
明るく輝く 竹串フィラメント |
これまた明るく輝きます。
タンマン管を用いて竹串フィラメントを作る方法は、広島文教女子大学の原田先生が、開発されました。私はこの方法を、大阪市立工芸高校の山田先生から教えていただきました。
また、電極にアルミホイルを利用することと、窒素ガスを充填することは、山田先生の発案です。
原田、山田両先生によると、竹串を1500℃で5分間加熱することで、グラファイトにすることができるそうです。その温度を実現するために、タンマン管とブタンガスバーナーの組み合わせがベストだそうです。
また、栃木県立黒磯南高校の寺田陽子さんから、生徒実験で竹串フィラメントを作る方法についてのアドバイスをいただきました。ありがとうございました。
このページは山田先生の許可を得て掲載しました。原田先生、山田先生、ありがとうございました。
上の実験はいずれもグラファイトに生じるジュール熱を利用しています。グラファイトが電気伝導性を持つことについては、次のように説明されています。
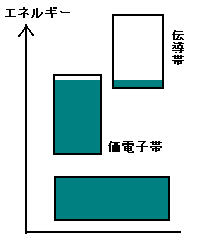 グラファイトのπ電子の価電子帯と伝導帯は、エネルギーバンドがわずかに重なっていて、π電子のうち、エネルギーの最大の電子は、価電子帯ではなくて伝導帯に入っている。そのため、ごく少量の自由電子とホールが存在する(このことは実験的に測定されている)。この自由電子とホールが電気伝導性に寄与する。
グラファイトのπ電子の価電子帯と伝導帯は、エネルギーバンドがわずかに重なっていて、π電子のうち、エネルギーの最大の電子は、価電子帯ではなくて伝導帯に入っている。そのため、ごく少量の自由電子とホールが存在する(このことは実験的に測定されている)。この自由電子とホールが電気伝導性に寄与する。
バンドの重なりはグラファイトの平面状の結晶同士の、層方向の相互作用によって生じるそうです。
バンドが一部重なり合うために電気伝導性を持つ物質は「半金属(semi metal)」と呼ばれ、他の例ではビスマスなどがあるそうです。半導体の場合はバンドギャップがあって、そこを熱励起で飛び越えることによって伝導性が生じますね。これに対し、半金属の場合は初めから(0Kでも)若干のキャリアを持つようです。
(以上、参考文献、「理化学辞典」、キッテル「固体物理学入門上」)
巷間、「グラファイトの伝導性は、π電子が結晶平面内で自由に動けるからだ」という話をよく聞きますが、それを主張する文献は見当たらないようです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 元へ戻る | 力学関連 | 熱力学関連 | 波動関連 | 電磁気関連 | 原子関連 | 科学の祭典 | リンク集 |